|
Part1 わがままなショパン date2197
音楽室から聞きなれぬタッチのピアノの音が響いてくる。ピアノなんてずいぶん久しぶりだ、そう思うと加藤は、つい、引き寄せられるように近付いていった。透き通った硬質な音だったが、そこには、息づまるようなかなしい懐かしさがあった。まるで、とても大事なものをどこかに置き忘れてしまっているような…。
そういえば、十年位前になる、週に二度ピアノの先生が来たっけ。銅像のようにどっしり後に構えて、練習風景を見ていた母。結局一年かそこいらでやめてしまったとき、怒りはしなかったけれど、淋しそうだった。若い頃、事情でレッスンを断念せざるをえなかった、ということだが、その時は知らなかった。知っていたら、少しは違っていたかもしれない。先生は、子供心にも美しい、しっとりとした日本人女性で、彼は妙に意地をはって、よく逆らったものだ…。少し淋しそうな、やさしい笑顔がきれいだった。
「ラヴェルだ」
彼はつぶやく。だれが弾いているんだろう。そっと近付いたつもりだったのに、音が断ち切られた。警戒と緊張。目が合う。気まずげにうつむく。山本だった。
知り合って三年たつが、こんな特技があるなんて全く気が付かなかった。
「習ってたの?」
「少し――。あとは自己流」
「どうして普段は弾かないんだ?全然分からなかった。俺、おまえの音好きだな」
すると山本はぶっきらぼうに答えた。
「やめたから。――でも見たら懐かしくなって…」
低めのAをひとつ、ぽんと叩く。ジムノペディの三番になった。
「やめちゃったって?」
「今のご時勢じゃ、ピアノ要らないと思ったから」
微かに震える和音を残して、手を止める。
「どうしてそんなふうに思ったんだ?」
時間もないくせに弾きにきて。また時間もないくせに聞きにきて。
「音楽なんて久しぶりだなあ。ずうっと訓練ばかりで、他に何もできなかったし」
「加藤くん、飛行機好きなんでしょ?」
「好きだけど」
「俺は…好きなだけじゃやっていけない。自分だけのものになったら仕事になり得るかどうか…分からない」
「それでピアノもやめたのか?どうして自分だけのものになっちゃいけないんだ?極めれば社会に貢献するし、いいんじゃないか?」
「それほど才能ない。仮にあったとしても、今の社会がそれを容認するかどうか」
加藤は、すべすべとした、少し色褪せた鍵盤を見た。しばらく使われていなかったのか、微妙に音が外れていて、それがまた魅力だ。
「今だから要ると俺は思う。こんな世の中だから、必要なんだ。他の人間だって欲しがっている」
山本はしばらく動かなかった。
「このまま逃げ道を作っていたら、飛行機に乗っていても集中できなくなる。何でも一生懸命にできない人間なんだろうかと思うのは、とてもつらい…」
「それなら、ひとつのことを思いつめていれば偉いのか?」
不意に山本は、嵐のように激しいエチュードを弾き始めた。
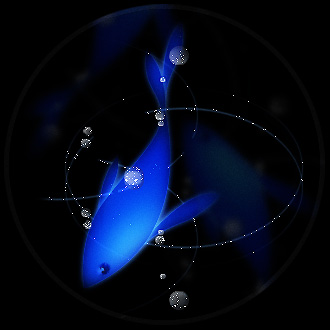
Part2 僕らは星のように孤独で date2201
たまの休暇をくりあわせて、飲み明かすことにした。
しかし、今起きているのは加藤と、口数の少ない、愛想の良いバーテンの二人きりだった。普段こんな飲み方ができないから、皆はめを外していた。
「ピアノが聞こえるな」
加藤は口にグラスを持っていきかけて止め、独り言をいった。
「上がだんすホールですからね、ピアノが有るんです」
「だんすの音楽にしちゃ静かだな」
「ええ。お連れ様が上がっていかれましたよ」
「山本、か」さっきまで、まるで視力のないような目で宙を見つめていた。
「ちょっと行ってきます」
階段の上のドアを開けるか開けまいか少し迷った。しかし入った。山本は振り返らなかった。ドビュッシーにかかりきっていた。時にもつれて乱れる指から生まれる音は、水のように冴え渡っていた。そして、思っていたよりずっと優しかった。それでいて、山本自身は全くの、冷たいほどの無表情だった。
大きな窓の黒い枠の向こうに地球が見える。加藤は何やら叫びだしたい衝動を必死に押さえた。ゆっくりと歩いていって、すぐ後ろに立っても、今日は山本は振り返らない。グラスを持っていたことを思い出して、口に運ぶ。妹の音色は明るくて、華やかだった。彼女の存在と同じく。そして先生の音色は上品で正確だった。母は――。
「好きなんだねえ、加藤」
突然振り返った山本は、加藤を軽く睨んだ後、彼には珍しく大きな声で笑った。それから加藤の腕ごとグラスを引き寄せ、一口、啜った。長い前髪をかきあげ、椅子の背にもたれて大きく息をつくと、「クラクラする」と言い、再び自嘲的に笑った。加藤は黙っていた。そして山本は再びピアノに向かった。叩きつけるような激しさだったが、途中で乱れると、不協和音をひとつ置いて手を止めた。背もたれに体を預けて目を閉じる。地球の照り返しで、彼の横顔はひどく蒼白く見える。
「――帰りたい」
「どこへ?地球?」
「違う」
既に地球に彼らの居場所はなかった。
「帰れるものなら」加藤は低い声で呟く。「しかし帰ってどうする」
肩に手を回して、また一口飲む。
「分からないけど!」
もたれ合っていると、眠り込んでしまいそうだ。加藤は目を閉じて静かに尋ねた。
「どうしておまえは諦めた?待っていたのに」
「待っていたって?」
少し沈黙があった。
「ずうっと前、俺の音が好きだって言ってくれたっけ」
「ああ」
山本の音色は思ったより優しい。そして、辛くなるほど、懐かしい過去を思い起こさせる。今はもう、その幻を抱いていることしかできない。
山本がすっと手を上げた。自分の肩によりかかる頭に軽く触れて言った。
「夢は全部終わった」
|