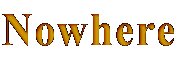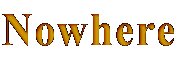|
「イライラするんだよ、最近」
ライターの蓋をかちん、かちん、と嗚らすのは、おそらく癖だ。表情はさほど不快そうには見えなかったが、規則正しい単調な金属音が、やや神経質に聞こえる。
「そりゃあ…」
少し離れてはいるが、隣のテーブルに若い女性の二人連れが席を占めていたので、加藤は言いかけた言葉を飲み込んで誤魔化した。
「まあ、いろいろ寂しいことも」
「そりゃてめえだよ」
山本は素っ気ない。
「それはともかく、会議が多いから? いっつもつまんなそうにしてるよな。損するよ、生意気に見えるよ。十分生意気だけどさ」
「余計なお世話です!」
ワインの瓶を取り上げて、ちょっとラベルを眺めた後、山本は自分のグラスに注いだ。6分目までを埋めて、瓶は空になる。加藤は早速見咎めた。
「おまえねえ、ちょっとは加減しろよ。俺4分の1くらいしか飲んでないぞ」
「じゃ、これいる?」
「いらないよ!」
さらに山本は、すぐにグラスを空けて言った。
「少し甘いなこれ」
「嫌なら飲まなくていいんだよ。アルコールと名がつきゃ何でもいいくせに、偉そうに」
それほど大きな声を出したわけではないのに、加藤の声はよく通る。ざわざわした話し声と、ぶつかりあう食器の音と、ブランデンブルク協奏曲にもかかわらず、隣の女性の一人がくすっと笑った。そして、友達をつっついた。
「加藤さんといると、何かと恥ずかしいことが多いから嫌だ」
山本は少し怒っている。
「あら随分ねえ。そりゃあ俺のせいじゃないよ。おまえの人間性に問題があるんだよ」
「もう少し声を低めてくれるとありがたいんだが!」
しかし加藤はさらに、にやにやしながら続けた。
「そういえば、山本さんはときどき馬鹿やっちゃうらしいねえ」
「誰がそんなこと言ったよ!」
「教えないよ。いじめるから」
「心外だなあ」
最後に残った、つけあわせに入っていたミニトマトに、ぷつっとフォークを剌す山本。
「遊んでないで、食えよ」
「誰かなあ、そんなこと、言ったの」
山本は不満げにぶつぶつ言った。
赤い、ざらついた果汁が皿の上にこぼれている。突き刺されて歪んだトマト。フォークが動かない。加藤はトマトから山本に視線を移した。山本は不思議に思い詰めたような、薄暗い顔をしていた。
今、何か差し障りのあることを言ったっけ。言ってないと思う。
どこを見ているのか、何を考えているのか分からない。会議の始まる前もそうだった。学生時代からの付き合いは長いが、前はこんなふうじゃなかった。
少し待ってみようかとも思ったが、加藤は再び、胸ポケットからペンを抜いて山本の頭を軽くはたいた。むっとしだような顔でこららを睨むのも、あの時と同じ。
「どっか行ってんじゃねえよ。全く、言ってるそばからしょうがないなあ。そのままにしておくとトマトさんが可哀相でしょ。なんだかグロだよ」
「シュールレアリズムの絵みたい」
「…と、それを食っちゃうんだね、おまえは」
「何なんだよ。加藤さんが食えって言ったから!」
「はいはいはいはい。でもしっかりしてよ。疲れてんの?」
「何それ。宮下さん?」
大いに棘っぽい口調で、山本は言い返した。実のところ、加藤は宮下が言ったことを忘れていたので、山本が即座にその名を挙げたとき、意外に思った。それほど仲が悪そうには見えないけれど。山本は、自分で考えているよりも宮下が苦手なのかもしれない。今度は明らかに苛ついた顔つきになった。
「疲れる理由なんかないよ」
声も尖っている。
「理由じゃ疲れめえ。心配事があるなら、喋っちゃいな」
「喋らせたいなら、もう一瓶持ってきな」
加藤は呆れて笑った。
「図々しいったらありゃしない。てめえなんぞに飲ましていたら身上潰してしまう。水でも飲んで我慢してろ」
「だったら、どうせすぐにコーヒーが来るからいい」
食事が済んでしまったので、少し手持ち無沙汰だ。加藤が、食事中は何が何でも禁煙を主張するため、山本はなおさら所在無さげだ。放っておくと、またどこか知らない世界に行ってしまうかもしれない。それとも、ライターの蓋を開け閉めしはじめるか…。山本は頬杖をついてテーブルの上に残ったティースプーンを取り上げ、引っくり返して眺めている。
「なんか面白いことないかな」
イライラする、と言った同じ口調で彼は言った。スプーンが金色にちかっと光った。とろっとしたくすんだ色の照明なのに、スプーンは思いの外鋭い光を小さく煌かす。
「なあ、宮下さんのこと嫌い?」
「嫌いじゃないよ」
間髪を入れずに返事が来た。
「ま、いいけどね。俺関係ないんだし。『部外者』だから」
山本は今度は返事をしない。スプーンをキラキラさせている。ちょっと嫌味を言ってやったつもりの加藤は面白くない。山本が何か言うまで喋りたくない気持ち。早くコーヒーが来ればいいのに。
「あ! さっきの、もしかして宮下さん?」
突然山本が大きな声を出した。
「何が」
「…俺がたまに馬鹿になるって言った奴」
「違うよ。やっぱり嫌いなんじやないの?」
「そんなに俺と宮下さん仲違いさせたいかい?」
山本は笑いながら問い返した。スプーンはもうテーブルの上に戻してしまっている。皮肉な調子はかけらもなかったが、加藤は言葉に詰まった。
「もし仮に、本当に嫌いだって言ったら、どうする? どうしてくれるつもり?」
むしろ楽しそうに、山本は言った。
「せめて、暴力はやめてね、とか、いじめないようにね、って言うしか」
本気の答えを期待されているのか、冗談にしておいたほうがよいのか分からない。それでも山本は、やっぱり笑いながら、「失礼だな」と言った。
コーヒーが来たが、そのとき急に店内が静かになった。音楽が止んだせいらしい。周りの人々も、いっせいに会話を中断した。山本は、新しい曲がかかるのを待っていたが、なかなか始まらない。特に何か喋りたいことがあるというのではない。しかし、こうまで静かだと、なんだか口を開きにくいのだ。
隣の女性たちは、声を殺して笑い合っている。何か笑われるようなことをしたっけ。加藤の声が大きいからいけない。それともやはり、あたりが静かすぎるので憚っているのだろうか。なんて気詰まりなんだろう。
「なに? どうかした? 変な顔して」
加藤がいつもの遠慮会釈のない口調で言った。ここだけ目立ってしまいそうで嫌だ。山本は制止しようとした。
「コーヒー、まずかったの?」
「そんなことないよ」
引っ張るような弦楽器の旋律が聞こえてきた。人々も喋りだした。ほっとする。ようやくコーヒーを味わって飲んだ。弦を強奏して曲が終わった。ずいふん短い曲だ。
いや、そんな筈はない。途中から始まったんだ。なぜ? 得体の知れない不快感が増した。酸素が足りないかのように、空気が重苦しい。
「具合悪いの?」
加藤が少し声を低めた。
「違う、ちょっと、BGM聴いてた」
「ああ、さっきから変わったな。ちゃんと聴いてなかったし、よく知らないけど」
「お隣さん、さっきからずっと喋ってた?」
「なんだそりゃあ。別に君のことは話してなかったと思うよ。…どうしたんだよ。何かあったのか?」
「何もないよ。でも、もう帰ろう」
残りのコーヒーを一気に片付けると、山本はすぐに席をたった。やけに優美で空虚なワルツが流れている。この音楽のせいか。血が障るのかもしれない。
|