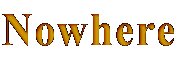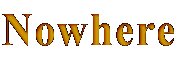|
岡崎が電話をとった。
「や、岡崎くんか。元気?」
加藤が笑いかけている。加藤にこう言われると、多少疲れたなあと思っていても、何となく陽気な気分になるから不思議だ。
「はーい元気ですよ! 誰をお呼びしましょうか。山本さんですか?」
「あ、いいや、そのつもりだったけれど君のほうがいい。丁度よかった。山本最近どうしてる?元気に働いてる?」
どんな答え方を期待されているのか、岡崎は迷った。
「と、言いますと…?」
「機嫌がいいとか悪いとか、具合悪そうだとか」
「見て、あまり分からないんです。怒ってるのかなあって思ってると、いきなり飴をくれたりするし」
「そっかあ…。じゃあ、お兄さんが編み出した判別方法を教えてあげよう。くっだらない駄洒落を言ってみるんだよ。機嫌がいいときは、どつかれるか、足を蹴られるかもしんない」
「じゃあ、機嫌が悪いときはどうなってしまうんですか?」
「ため息をついたなり、あとはシカトされる。しばらく口をきいてくれないかもしれないな」
それが分かっていながら、そんなことをできる度胸があるなら、山本が不機嫌にしていようがいまいが、気にならないのではないだろうか。第一、それで不機嫌だと分かったとしても、そのときには既に遅いではないか。岡崎は考えた。
「それは困ります。あと、駄洒落がつまらな過ぎて機嫌を損ねちゃうことはないんでしょうか」
「それ、俺への挑戦? 僕だったらもっとうまいこと言ってやるのに、とか」
加藤がにやにやする。
「そんなことありませんよ!」
「何にしろ一晩待てば大丈夫だよ。たかが山本じゃない」
「でも睨まれると怖いです」
「変な話になっちゃったなあ。じゃあ具体的に聞こう。山本、突然ぼーっとしちゃってることある?」
「たまに、あります」
「仕事中に?」
加藤の声が若干鋭くなった。岡崎はあわてて、「仕事中はないと思います。移動の空き時間とか、食事のときなんかに」と、答えた。
「仕事に差し障りがないなら、いいんだけどね」
わざとぞんざいな喋り方をしたが、歯切れの悪さが残る。
「ときどき暗い、思い詰めた顔なさってます。つい頼ってしまうけど、本当はまだ若いんだよな、迷惑かけちゃいけないなって思います」
「君らはそんなこと心配しなくていいんだよ」
「すみません。出過ぎたことを、言いました」
「そんなんじゃないって。まあとにかく、岡崎くんは何も心配しなくていいから。こんな電話掛けといてナンだけどさ。あいつには内緒にしといて」
「分かりました」
電話を切り、振り返ったとき、さすがの岡崎も全身が凍り付いた。
山本が立っている。腕組みをし、これまで見たことがないほど激しい眼差しで、そのため目元がきっと切れ上がって見えた。
何か言わなければと思い、口を開きかけたが、言葉が出てこなかった。大柄なほうでもない、むしろ優男の部類に入るような山本だが。ただ漠然と岡崎は、もう終わりだ、と思った。
「何の話?」
冷たい瞳がちらりと動いて、電話機から岡崎に移った。
どこから聞いていたのか知らないが、黙って後ろに立っているなんて人が悪い。思っても、言えなかった。別にまずい話をしていたわけではないのに。
「加藤には俺から連絡をする。余計な真似をするなって。君は、君の仕事だけに専念してください」
怒鳴られたほうがまだよかった(怒鳴られる理由はないが)。冷ややかな調子がかえってきつかった。今まで考えていたより、ずっときつい。どうしてそこまで拒否するんだろう。
|