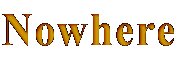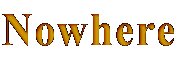|
最近、学生時代の友人のヘルマン・シュタインがこちらに乗ている。体をこわして事務系に移ったが、落ち着いていて穏やかで、そばにいると何となくほっとするタイプの人間だった。山本も加藤も、たいへんにお世話になった。なりっぱなしだ。よく、今まで付き合ってくれていたと思う。久しぶりに会って、最初に山本が考えたのは、こういう人間がチーフをやってくれれば何かとうまく収まるのに、ということだった。
ヘルマンも、山本に会うなり「何だかやせたね」と言った。そうかな。この間もそう言われたけど、ひどい目に遭ったよ。ヘルマンは黙って微笑んだ。何もかも知っていそうな、また逆に、何も知らなくてもいい、そんなことは問題ではない、と言っているような温かい目をする。
「お節介なようだけど、君も加藤ももう少し肩の力を抜いたら」
他の人間(たとえば加藤)に言われたら腹が立つような言葉も、ヘルマンからだったら受け入れることができそうな気がする。
そのうち、加藤の都合も聞いて、飲みにいこうという話になった。
あまりにも退屈なので、テレビやラジオのチャンネルをひっきりなしに替えていた。まだベッドに入る気はしない。しかしどれもつまらない。活字を読むのは少し気が重い。山本は意地になって、音を探し続けた。
クラシック音楽に行き当たった。聞いたことがある旋律だ。だが、何かがささくれて傷つき、不快な感じのする曲。どこで聞いたんだか…。荒れ狂った厚ぼったい和音が低く響いた瞬間に、長沢を思いだした。あのときの曲か。褐色の深淵に長沢が落ちていく。落ち続けていく。この低音は底無しだ。冗談じゃない。とても聞いていられない。スイッチを切った。しかし音楽は鳴り続けている。鳴っているのはラジオではないのか、頭の中なんだろうか。そんな筈はない、別のスイッチを間違って切ったのだ。きっとそうだ。
不意に肩を叩かれた。ぎょっとなって振り返ったが、知らない中年男だ。額が広く、頬髭を生やしている。誰? 詰問したかったのに、声が出なかった。男は灰色の大きな目で山本を見つめ、何事か喋った。しかし意味が分からない。
もしかして、チャイコフスキイ? ようやく作曲家の名前を思い出す。しかし、肖像画で見たその人は、こんな顔ではなかったような気がする。もっと目が鋭く、人を寄せ付けない厳しい顔つきをしていたと思う。この男は、どちらかというとイコンに似ている。哀しげで、肩を叩き、なだめるような口調で喋っている。
何を言っているか、分からない。山本は苛々しながら、言い返した。何しにきたんだ。男は目をそらさずに首を振っている。
「何も知らないくせに!」
男はさらに首を振りながら、たどたどしく答えた。
「分かるよ、分かる…」
両手を広げた。
耐えきれなくなり、その声を振りはらってスイッチを切った。やはりさっきはまだ切れていなかったのだ。主電源も落とした。上着だけを抱えて部屋を出た。ものすごく気持ちが悪い。三半規管から酔いが来たような。動きたくはないが、あの部屋にいたくない。何もかもが不快だが、中でももっとも許せないのが自分だった。自分の存在が耐え難い。
どうしよう。公衆電話を探して、ヘルマンを呼び出した。
「いま暇? どこかに飲みにいこうよ」
ヘルマンは微笑した。
「外に出ることはないよ。俺のところに来れば。酒ぐらいあるから」
「じゃあ行く」
どうせ同じ建物の中だが、とりあえず上着を羽織った。俺危ないかもしれない。無意識に口をついて出た言葉に、自分で驚いた。
|