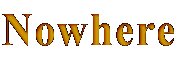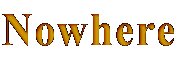|
山本は黙っていた。頬杖をついたなりで、尖った顔をしている。突然喋りはじめた。何かと思って聞いていたら、ばか話だった。仲間内の失敗談やら何やらが多かったと思う。不機嫌そうな表情で話しだすから、最初は、話の対象への不満を言うのかと思った。しかし、注意して聞いていたが、そんなメッセージは読み取ることができなかった。
電話を掛けてきた時の顔が山本らしくなかったから、外に出さずに自分の所に呼んだのだ。まるで、自分が死ぬか、他人を殺しに行くか、というぐらい思い詰めた様子に見えた。珍しいことだ。
何かあることは間違いないのに、それらしいことを言いださないから、気になる。言いたくないのか。聞かれるのを待っている……とは思えない。
山本は昔から、感心するほど強気だった。何でもよくできたし、自信もあるのだろう。それが生意気に見えるらしく、先輩たちが小面憎がっていたのを、ヘルマンは知っている。あいつは可愛げがない。そんなことを言われても困るのに。山本は擦り寄っていくタイプではないのだから、仕方がない。
何があっても平気、って顔してる。口を曲げてそう言った者もいた。悩み事なんかないだろうな、好きなように生きて、言いたいことを言ってさ。
できて当たり前だと思われていたのだから、平気な顔をしているほかなかった筈だ。他の連中ができなくても、山本や加藤は、やらなくてはならなかった。教官も、同期の連中も、皆そう思っていた。でも、それは辛いんじゃないだろうか。
山本は、その後しばらく黙っていた。時々、思い出したようにウィスキーのグラスを口に運んだ。
「やっぱり帰る」
出し抜けにそう言うと、立ち上がった。
「また来いよ」
山本は振り返って、口元だけで笑った。他に表情が浮かんでいないから、異様だ。そして出て行った。目が届くように泊めて様子を見ようと思っていたが、敢えて引き留めることは止めた。
頃合を見計らって電話を掛けてみる。
もう寝ているかも知れないと思ったのに、山本は着替えもしていなかった。
「起きてたのか」
「何だよ、電話しといてそれはないだろう」
「悪かったな。早く寝なさいよ」
山本は微かに笑ったらしい。
電話を切った。
駅だ。
線路がある。列車はずっと来なかった。
どこか、ここからそう遠くない所で事故があったらしい。しかし、駅はひどく静かで、待っている人はほとんどいない。枯れたようにすら見える白っちゃけたホーム。駅員が2人、無言で、しかし慌ただしく通り過ぎていった。バケツを両手に提げて。バケツは4つ。血に塗れた4つのバケツ。慌てて目をそらした。それなのに、焼き付けられたように、いつまでも、バケツが頭から離れない。駅員の後ろ姿が見えてしまう。遠ぎかっていく。両手には、バケツ。不意に、ずれてだぶった足音が聞こえた。
見たくはないのに、何かを探してちらちらと線路を見やる。所々に血が落ちている。やっぱり急いで目をそらした。
列車が入ってきた。前面に血飛沫が飛んでいる。止まらないのか、スピードも緩めない。若い女がふわりと近付いた。吸い込まれるように前に出た。列車が止まらない。通り過ぎた。音もなく。列車も女もいない。
探していたものが見つかった。
警報が出た。みんなでぞろぞろと地下に避難する。水が必要だ。各々の手にタンクを持って、黙々と、階段を下りていく人々。どうして誰も、何も言わないんだろう。食糧は? 小さな子供までもが、黙って手を引かれている。どんな表情をしているのか、顔が見えない。
階段の途中で衝撃があった。大きく揺れて、壁がびりびりと痺れた。一瞬足を止めた人々は、また、何事もなかったかのように、動きだした。下りて下りて下りて、少しずつ暗くなる。地下都市にはエレベーターがあった筈なのに。すぐ後からついてくる、大量の足音に圧迫されるように、階段を下り続けた。
放射能が満ちているから、外には出られない。もう、しばらくここに閉じこめられている。
厚い厚いガラス越しに外を眺めている。目の前に、大きな正教の寺院がある。半ば崩壊しているが、よほど丁寧に建てられたのだろう、玉葱型の塔が残っている。灰色に潰れた、死んだような街だが、「玉葱」の所々に、薄く草が生えはじめていた。こんなに地上の高いところで。何だかほっとする。
寺院の屋根伝いに、何かが蠢いている。人だ。黒っぼい衣服に、頭からショールを被って、髑髏のマスクを付けている。外はまだ、人間がいられるだけの環境になっていない。致死量の放射能の海だ。3人、老婆だろうか、屋根の上で踊っている。
マクベスの魔女! 窓から離れようとした。いきなり、ぐいと窓を引き開けられた。髑髏のマスクを引き除けて、老婆が無邪気に笑いかける。骨張った指が、物凄い力で腕を引く。
「新鮮なジャガ芋や玉萄黍はいかが?」
夢見が悪かったので、頭が重い。自分が分からない。内側から押し潰されそうだ。今まで意識しなかった、全く違う自分が中にいる。存在、考え方、すべてが許せない。紛れもなくそれは自分なのだから。今まで生きてきた年月が、一気に崩れたと思った。そんな大袈裟な、しかし、見たくない自分を見せつけられた。
ヘルマンが近付いてきた。暖かい声で、やあ、と言った。
「元気ないね」
「変な夢見てさ」
「へえ、どんな?」
ヘルマンに近寄らない方がいい。あいつが出てくる。あいつは隙があれば、すぐに浮き上がってくる。
不意に、擦れてくすんだ、粒立った音が聞こえた。山本はどきっとした。
「何、あの音。…ファゴット?」
「給湯室のブザーだよ」
ヘルマンが不思議な目で見る。ファゴット? 何を言ってるんだろう。
「……線路で小指を見付けた。摺り潰されて平べったくなっていたけど」
「小指? 誰の?」
山本は少し自信なさげに答えた。
「俺の、かな」
「なかなか凄いね。線路か。何かトラウマでもあったかなあ」
言いながら、不思議な目で見る。何か気付いたのだろうか。山本は睨み返す。
「ちょっと待てよ。何やってるんだ」
ヘルマンが腕を掴んで持ち上げた。何やってるんだとは、お前のことだ、と思ったが、自分の掌を見て驚いた。いつのまにか握り締めた爪が皮膚に喰い込んでいる。三日月型のうす赤い傷が、指の数だけ並んでいた。ぎょっとした。
「駄目だよ。爪は雑菌だらけなんだし」
「雑菌だらけですみませんねええ」
多少気を悪くして、山本は答える。ヘルマンは笑った。
「気をつけろよ。やっと山本らしくなったな。あとでじっくり、グロで変な夢を教えてくれ。じゃあ」
爽やかに手を挙げて ヘルマンが立ち去った。俺が不安定に見えたから、声をかけたってことか。どうしてこう、お節介な人間が多いんだろう。
俺は違う。彼は、対象のはっきりしない怒りを感じ、きっとなって、足早に、仕事場に向かって歩きだした。
「違う」
俺は長沢とは違う。
|